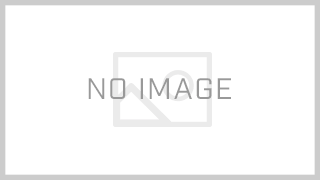【クレーンゲームのコツ】・橋渡し(箱型)の取り方を徹底解説

クレーンゲーム(UFOキャッチャー)効率良く取りたい方へ
クレーンゲームをプレイしたことがあっても、フィギュア(箱型)の景品にトライしたことがない人は多いと思います。
今回は「最近クレーンゲームを始めたのでコツを知りたい」「これからクレーンゲームに挑戦してみたい」という方に向けて、フィギュア(箱型)で定番の設定「橋渡し」の実践的なコツをわかりやすく解説します。
今回お伝えするコツはゲームセンターだけでなく、オンクレ(オンラインクレーンゲーム)でも使える内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
クレーンゲームの基礎知識
ゲームセンターを訪れたことがある方はご存知の通り、クレーンゲームにも様々な種類があります。
景品について
ゲームセンター専用に作られた景品のことをプライズ品と呼びますが、最近では様々なものがクレーンゲームの景品として採用されています。
- フィギュア
- ぬいぐるみ
- 食料品、お菓子、飲料
- 日用品
- 雑貨
アニメや漫画にあまり興味がない人でも楽しめるラインナップが増えたことも、近年のクレーンゲームブームを後押ししている要因でしょう。
また、オンクレではゲームセンター以上に様々な景品を取り扱っています。
たとえば、タイクレでは約5,000種類以上の景品が揃っており、ゲームセンターにはない限定仕様のフィギュアやコンビニ・飲食店などで使える引換券などを取り扱っています。
DMMオンクレでも引換券を取り扱っており、タレントやインフルエンサー、VTuberなど、多種多様なコラボグッズも取り扱っています。
設定の種類
クレーンゲームには様々な設定がありますが、大きく確率機と実力機に分けられます。
アームを操作して景品を狙うという点では共通していますが、確率機は投入回数やタイミングによってアームの力が変動するのに対して、実力機はアームの強さや動きが常に一定で、結果はプレイヤーの操作に左右されます。
| 実力機 | 確率機 | |
|---|---|---|
| アームの力 | 変化しない | 一定のタイミングで変化する |
| アームの本数 | 2本 | 3本(ただし例外もあり) |
| 景品の種類 | フィギュアが多い | ぬいぐるみが多い |
| ゲームの難易度 | プレイヤーに依存する | ほとんどプレイヤーに依存しない |
今回は実力機の中でも王道の「橋渡し」設定のコツに絞って解説します。
クレーンゲームの確率機のコツについては以下の記事で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
「橋渡し」とは
「橋渡し」とは真ん中の2本のバー(橋)のすき間から景品を落とす設定のことを言います。

主にフィギュアなどの箱型の景品に採用されることが多いですが、食料品やぬいぐるみなどにも見られることもあります。
また、橋幅が左右で異なる「末広がり(ハノ字)」の橋渡しもありますが、基本的な攻略法は同じです。
橋渡し 攻略の基本とコツ
それでは橋渡しを攻略する上で抑えておくべき基本とコツを8つ厳選してお伝えします。
- 橋幅
- バーの種類
- アームパワー
- アームの開き幅
- アームのねじれ
- 爪の向き
- 景品の大きさや形状
- 重心
1. 橋幅
ここでいう橋幅とは景品が落ちる真ん中の2本の橋のすき間の幅を指します。

橋幅は店舗や景品によって異なりますが、基本的に景品に対して橋幅が広い方が取りやすいです。
橋幅が広ければ色々な位置や向きで落とせるのに対して、橋幅が狭ければ特定の落とし方しかできないので、精度の高い操作が必要になります。

一般的に新景品や人気景品などは、橋幅が狭く設定されていることが多いので注意が必要です。
2. バーの種類
橋渡しのバーには、以下の2種類があります。
- 滑り止めがあるバー
- 滑り止めがないバー
滑り止めがあると景品が動きずらく、位置をキープしやすいのが特徴です。
滑り止めが無ければ必ずしも簡単だという訳ではありませんが、滑り止めの有無で攻略の方法が大きく変わってきます。
滑り止めの見分け方
滑り止めの有無は、色を見れば一発で判断できます。
銀色や白色のバーは滑り止めが付いておらず、ピンク色のバーは滑り止めが付いています。

ただし、中には白色や透明の滑り止めもあるので、バーにゴムチューブのようなものが巻かれていれば滑り止めがあると考えてOKです。
まれに、ホコリやゴミ、チューブの劣化などで滑り止めが十分に効いていないこともあるため注意が必要です。
3. アームパワー
アームのパワーが弱い場合、どうしても時間がかかってしまったり、途中で動かなくなってしまうことがあるため注意が必要です。
もし、最初のプレイでほとんど景品が動かなかったら、撤退するのも一つの手段です。
ただし、アームパワーが強ければ単純に難易度が下がるという訳ではありません。
よく動いたとしても、繊細なコントロールができなかったり、橋幅が狭ければ、なかなか取れないこともあります。
また、橋幅が広ければ、多少アームパワーが弱くても早くとれることもあるので、その他の要因と合わせて総合的に判断するのがおすすめです。
4. アームの開き幅
アームの開き幅も重要なポイントです。
クレーンゲームでは片方のアームをギリギリまで寄せて動かすことも多いので、できるだけ早くアームの開き幅を見極めるようにしましょう。
アームの開度はお店側で設定できるようになっていますが、基本的にはアームが閉じた状態の肘の部分までが開き幅になることが多いです。

閉じた状態のアームの肘を基準に、それよりも大きいのか、小さいのかをチェックすると開き幅を掴みやすいです。
5. アームのねじれ
ほとんどのアームは時計回りに少しねじれながら下降することが多いです。
そのため、ねじれを考慮してアームの位置を決める必要があります。
実は、このねじれを利用することで、攻略の幅が広がります。
たとえば、片方のアームをバーに乗せて、もう片方のアームで景品の端を引き上げるなどが可能になります。
まれに、全くねじれない場合やねじれが逆(反時計回り)の場合もあるので、最初のプレイでチェックしておきましょう。
6. 爪の向き
意外と見落としがちなポイントなのが爪の向き。
アームが閉じた状態で爪がしっかり曲がっていると、景品を動かしたり、持ち上げたりしやすく、景品を動かしやすくなります。

パワーがありそうなのに、いまいち景品が動いてくれないという場合は爪の向きが関係しているかもしれません。
7. 景品の大きさや形状
橋渡しは箱型の景品が多いですが、様々な大きさや形状の箱があります。
基本的な攻略方法はあまり変わりませんが、箱によって動きが異なるため注意が必要です。
通常箱

最も多くの景品に採用されており、攻略がしやすい形状です。
ただし、重心によって難易度が変わるので油断は禁物です。
長箱

バンプレストの「Grandista」シリーズやフリュー(FURYU)の「Trio-Try-iT Figure」シリーズなど、サイズが大きいフィギュアに多く見られる箱の形状。
重い景品も多く、箱の向きによってうまくアーム下までが入らないことがあるので注意が必要です。
立方体

あまり多くはありませんが、タイトーの「Desktop Cute」シリーズや雑貨などに見られる形状。
転がりやすいのが特徴で、橋渡しの場合難易度が高いです。
ミニ箱

セガの「ちょこのせ」シリーズなどに見られる形状で、アームに対して景品が小さく、軽いため動きやすいのが特徴です。
その他
食料品やぬいぐるみなど、まれに箱型以外の景品もあります。
基本的な攻略法は同じですが、穴にアームを刺したりなど個別の攻略要素がある場合があります。
8. 重心
重心とは景品の重さの中心(いちばん重い位置)のことです。
重心の位置は上下・左右・表裏と景品によって異なります。
また、景品によっては中で動いて重心が毎回変わるものもあります。
重心を意識しなくても取れることはありますが、正しく理解しておくことで確実に手数を減らせます。
重心から離れている位置が動きやすい
アームのパワーが一定なのに、狙う位置によって動きやすさが変わることがありますが、これは重心が大きく関わっています。
重心から離れている位置は動きやすく、重心に近づくほど動きずらくなっています。
たとえば、右下に重心が偏っている景品は左上が一番動きやすいです。

重心の調べ方
景品の重心情報は、専用のサイトやSNSに掲載されていることがあります。
ただし、新景品など景品によっては情報が出ていない場合もあります。
そんな時は最初の1プレイで確認する方法も有効です。
景品のど真ん中狙い、浮いてくる方をチェックします。
たとえば、真ん中を持ち上げて景品の下側が浮いてきたら、重心は上側に偏っていると分かります。

橋渡しの取り方(ワザ)のコツ
これまで説明してきたように、橋渡し設定では様々な条件が絡んでくるので、特定の攻略方法はありません。
状況に応じたアーム操作が求められます。
最初は難しいかもしれませんが、そこがクレーンゲームの奥深さであり、魅力的なポイントでもあります。
ここでは、最も代表的な取り方である「縦ハメ」の取り方とコツを紹介します。
縦ハメの取り方とコツ
縦ハメは景品を縦向きのまま少しずつ奥に移動させていき、最後に真ん中の隙間から落とす方法です。
汎用性が高く、ほとんどの設定で使用できる取り方なので、最初に覚えておきましょう。
ただし、滑り止めが機能していない場合は、奥に移動させても景品が戻ってきてしまい、うまく取れないことがあるので注意が必要です。
①奥側の角にアームを入れる
まずは片方のアームを寄せて、奥角を狙います。
ギリギリ端を狙った方がよく動くので、できるだけアームを寄せてあげるのがコツです。

箱が少し奥に移動し、斜めになります。

②逆側の角にアームを入れる
今度は逆のアームを寄せて、反対側の角を狙います。

③何度か左右の角近くにアームを入れて景品を「ハメる」
繰り返し左右の奥角を狙って動かしていきます。
このとき、手前の角とバーのすき間の対角の角を狙うのがポイントです。

何度か奥の角を持ち上げることで、景品が少しずつ奥にいき、手前の角がバーの下に落ちていきます。

この状態を「ハマる」と呼び、順調に進んでいるサインになります。
アームのパワーが弱いと少しずつしか動かないため、ハマるまでに時間がかかるかもしれませんが、諦めずに進めましょう。
何度プレイしてもハマらない場合は、寄せ方を変えたり、手前側を狙うなど、状況に応じて戦略を見直す必要があるかもしれません。
④さらに奥角を狙ってゲット
さらに交互に片方のアームを寄せて奥角を狙います。

繰り返し交互に奥角を狙っていくのですが、このときも手前の角とバーのすき間の対角の角を狙いながら進めていきます。
手前の設置が少しずつ小さくなり、少しずつ景品が立ち上がってきます。

このとき、動かないからといって手前を狙うと箱が戻ってくるので注意が必要です。
⑤景品を立ち上げるようにしてゲット
最終的に手前の接地面が小さくなり、ほとんど落ちた状態になったらすき間がある方の対角を片アームで引っ張るようにすると、奥が持ち上がり接地点が外れて落ちてくれます。


最後が決めきれない場合は、少し手前を狙ったり箱の裏をなぞるようにするなど、狙う場所を変えてみることで落ちてくれることがあります。
今回は奥に移動させる方法を紹介しましたが、箱の重心やバーの位置によっては手前に移動させる方法(逆縦)も有効です。
クレーンゲームの攻略に役立つ豆知識
技術的なことではありませんが、以下のような点を抑えておくと取りやすくなるかもしれません。
お店選びが重要
実はテクニックと同じくらい重要なのがお店選びです。
クレーンゲームはプレイする前から始まっていると言っても過言ではありません。
お店によって設定のクセがあり、取りやすいお店は全体的に取りやすい傾向があります。
事前にGoogleマップの評価をチェックしたり、実際に足を運んで、橋幅やアームパワーをチェックしてみましょう。
また、優良店を見つけたら、何度か通って攻略方法を考えてみるのも楽しいですよ。
攻略方法を確立しておくと、新景品が出たときにすぐにゲットできるのでおすすめです。
優良店の見極め方の詳細は以下もチェック!
ハイエナ
他の人が途中で諦めた台をプレイすることを「ハイエナ」と呼ぶことがあります。
景品が動かなくて諦めてしまったのか、資金が尽きてしまったのか分かりませんが、かなりいい形で放置されているケースもあります。
ただし、ハイエナをする場合は前の人が完全に諦めたのを確認しましょう。
捨て100
「捨て100」とは最初の1プレイ(100円)を捨てることをいいます。
直接的に獲得に繋がるプレイにはならない可能性もありますが、台を見極めるための有効な手段です。
この記事でも、いくつかポイントを紹介してきましたが、実際にプレイしないと分からないことはかなり多いです。
捨て100で見極めるべきポイント
- 景品の重心
- アームパワー
- アーム開度
- アームのねじれ
- 移動範囲
- 下降制限
また、捨て100をするときに、おすすめなのが景品のど真ん中を狙うことです。
景品の重心やアームのパワー・開度など重要な情報が分かるだけでなく、運よく真ん中で持ち上げる(バランスキャッチ)ことができれば1発ゲットの可能性もあります。
因みに、筆者もバランスキャッチを利用した1発ゲットを何度か経験しています
筐体(きょうたい)の種類
筐体とはクレーンゲームの台のことですが、実は様々な種類があります。
それぞれの筐体のクセを理解しておくと、攻略に役立つことがあります。
ここでは、橋渡しによく使われる代表的な筐体を紹介します。
UFO CATCHER 9(UFOキャッチャー9)

セガのUFOキャッチャーシリーズ(2本アーム)の第9世代として2014年に登場。
ラウンドワンなどの大手ゲームセンターでも定番の筐体です。
最新の筐体に比べて、移動するときにアームがやや揺れる印象。
「UFO CATCHER 9 second」や「UFO CATCHER 9 third」などの同シリーズの後発台もよく見られますが、基本的な動きは変わりません。
UFO CATCHER 10(UFOキャッチャー10)

UFO CATCHER 9の次世代機として2023年に登場。
UFO CATCHER 9に比べて滑らかに移動するのが特徴。
また、箱のギリギリ端を狙ったときにぬるっと避けるようにして下降をします。
クレナフレックス

2004年にナムコから登場したクレナシリーズの初代機。
アームの本体部分が丸くなっているのが特徴で、まだまだ現役で稼働しているところも多く、非常に人気な筐体です。
本体に対してアームが長い台が多く、開き幅が大きい傾向にあります。
また、下降時の押しが強く、強引にアームを寄せて景品に当たっても下までいってくれることが多いです。
クレナ3

2022年に登場したクレナフレックスの後継機。
液晶タッチパネルが導入され、レバー操作にも対応しているのが特徴です。
店員さんに相談
どうしても取れない場合は店員さんに相談するのも有効な手段です。
その際、以下のように具体的に伝えるのがポイントです。
- 3,000円くらい使ったのですが、なかなか取れなくて…
- 奥を狙っても手前を狙っても動かず、どこを狙ったらいいかアドバイスをもらえませんか?
- アームが届かない位置に景品がいってしまったので、位置を調整してもらえますか?
特に、設定に問題がある場合は、早めに対応してもらうことで無駄な出費を減らすことができます。
店舗によっては「位置調整は初期位置のみ」などのルールが決められている場合があるので注意が必要です。
店舗のルールは筐体に貼ってあるので、事前にチェックしておきましょう。
コツを抑えて橋渡しに挑戦しよう!練習はオンクレがおすすめ
橋渡し設定では様々な条件が絡んでくるので、特定の攻略方法はありません。
状況に応じたアーム操作が求められます。
最初は難しいかもしれませんが、そこがクレーンゲームの奥深さであり、魅力的なポイントでもあります。
今回紹介したポイントを活かして、ぜひ橋渡しにチャレンジしてみてください。
オンクレの中にも橋渡し設定があり、ほとんどのアプリでは無料プレイや試遊台などでいつでもどこでも練習できます。